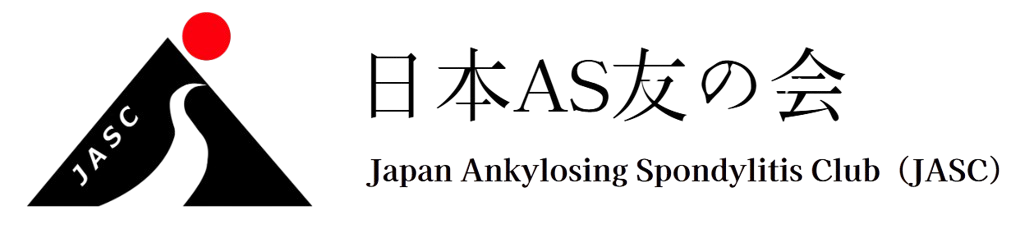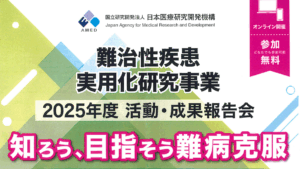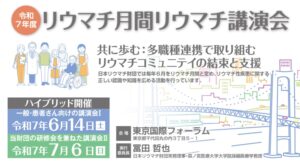日時:
場所: ハイブリッド開催
開会挨拶 (井上医療部長)
井上医療部長より開会の挨拶と、北海道支部会の報告があった。会場は札幌市民交流プラザで、午後2時半から6時まで支部会を開催、その後4時から懇親会を予定している。支部長のゆみ子氏が中心となり準備を進めているものの、ご本人も重症であるため運営をサポートする人材を募集していることが報告された。ITスキルを持つ若い世代の積極的な参加を呼びかけ、50代でも歓迎であると述べた。観光で札幌を訪れる会員の参加も歓迎とのこと。
脊椎関節炎(SpA)の最近の話題 (多田医師)
多田医師より、SpA、特に強直性脊椎炎(AS)と非放射線学的体軸性脊椎関節炎(nr-axSpA)に関する最新の研究知見が報告された。両疾患は同一疾患の異なる段階と捉えられてきたが、nr-axSpA患者が必ずしもASに進行するわけではないこと、自然寛解する例や進行が緩やかな例も存在することが説明された。
多田医師は、順天堂大学病院を含む4施設で収集した日本人AS患者111名の臨床データを基に、男女比、発症年齢、HLA-B27陽性率、罹病期間、疾患活動性などの特徴を解説。ASは男性に多く、発症年齢は20代前半が多いこと、診断確定までの期間が平均12年と長いこと、HLA-B27陽性率は75%程度であることなどが報告された。
さらに、日本人nr-axSpA患者49名とAS患者111名の比較も行われ、nr-axSpAでは女性の割合が比較的高い傾向にあること、罹病期間は短い傾向にあるものの、疾患活動性はAS患者とほぼ同等であること、HLA-B7陽性率はAS患者より低い48%程度であることなどが示された。これらの結果は海外の研究報告と概ね一致するとのこと。
治療に関しては、早期診断・治療の重要性が改めて強調され、疾患の多様性を考慮した上で、個々の患者に最適な治療戦略を立てる必要性が述べられた。また、HLA-B27検査が保険適用外である現状や、nr-axSpAが指定難病に含まれていないことなど、診断と治療における課題も示された。
ASとnr-axSpAの臨床像と治療 (小林茂医師)
小林医師は、ASとnr-axSpAの臨床像、鑑別診断、治療法について解説した。特に、生物学的製剤(バイオ製剤)の適切な使用時期、効果と副作用、治療継続率などについて詳細な説明があった。
診断においては、画像所見、血液検査値(CRP)、HLA-B27、喫煙歴などを総合的に判断する必要性を強調。また、45歳以上での発症は稀であり、高齢発症の場合は他の疾患を疑うべきであると述べた。
治療に関しては、バイオ製剤の効果が高い一方、高額であること、副作用のリスクがあることなどから、安易な使用は避け、患者との十分な話し合い(シェアード・デシジョン・メイキング)に基づいて治療方針を決定する重要性を訴えた。
また、バイオ製剤の継続率に関するデータも示され、一次無効、二次無効、副作用、経済的理由などによる治療中止の割合、および2剤目以降のバイオ製剤の効果と継続率について解説があった。
さらに、薬物療法に加えて、ストレッチや運動療法、温泉療法などの非薬物療法の重要性も強調。患者個々の病状や生活状況に合わせた包括的な治療アプローチの必要性を述べた。
障害年金制度の解説 (田中社会保険労務士)
田中社会保険労務士より、障害年金制度に関する詳細な説明が行われた。受給資格、等級認定基準、請求手続き、支給額、注意点などについて、スライドを用いて分かりやすく解説。
初診日の確定、病歴・就労状況申立書の記入、診断書の入手など、請求手続きにおける重要なポイントが説明された。特に、人工関節置換術後における障害等級認定基準の変更点、複数の障害がある場合の等級認定、障害年金と他の社会保障制度(傷病手当金、雇用保険、生活保護など)との関係について詳しく解説された。
また、障害者手帳の申請方法やメリット(税金の優遇措置、公共交通機関の割引など)についても紹介があった。
質疑応答
会場およびオンライン参加者から、以下の質問が出され、田中社会保険労務士と医師陣が回答した。
- 血圧と痛みの関係について
- 人工関節置換術と障害者手帳、障害年金について
- 麻酔への恐怖心について
- 就労規則からブラック企業かどうかを判断する方法について
- 老齢年金と障害年金の同時受給について
その他 (井上医療部長)
AS友の会の活動を通じて、患者が利用できる公的支援制度の情報提供や支援の重要性を改めて伝えらえた。患者自身も積極的に情報収集し、権利を適切に行使するよう呼びかけた。
診断書の記入について、医師の負担軽減のため、患者が事前に病状や日常生活における困難さをまとめたメモを用意することの有効性を教えていただいた。
井上医療部長より閉会の挨拶があり、盛況のうちに総会は終了した。