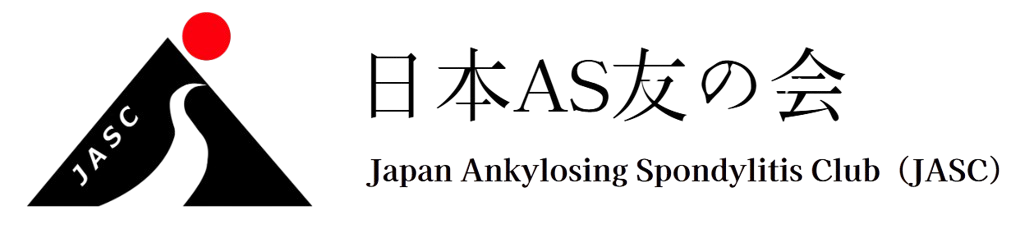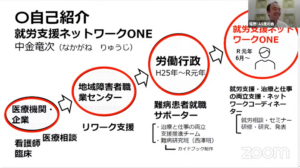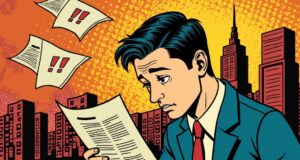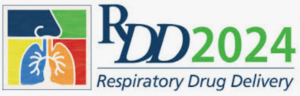「働きたいけれど、働けない」——そんな悩みを抱える人は少なくありません。病気や障害、長期間の引きこもり経験がある人にとって、社会復帰の第一歩を踏み出すことは簡単ではないでしょう。
今回は、社会福祉法人中心会が取り組むユニバーサル就労支援の事例を紹介し、実際にどのような支援が行われているのか、そして社会復帰のための具体的なステップを解説します。
ユニバーサル就労支援とは?
ユニバーサル就労支援事業は、2014年に社会福祉法人中心会がスタートした就労支援プログラムです。特徴として、
✔ 年齢・病気・障害の有無を問わず、「働きたいが働けない」人を支援
✔ これまでに約440名を支援
✔ 「すぐにフルタイムで働くのが難しい人」向けに、段階的な就労訓練を提供
「仕事が見つからない」「ブランクが長すぎて不安」など、一人ひとりの状況に応じた支援が行われています。
病気や引きこもり経験者が直面する課題
ユニバーサル就労支援の対象者には、さまざまなバックグラウンドを持つ人がいます。
引きこもり経験者(10代~50代)
- 学校不登校→就職活動がうまくいかず、そのまま社会から孤立
- 長年のブランクによる「働く自信の喪失」
長期間仕事をしていない人
- 育児や介護のために仕事を辞め、そのまま復帰できずにいる
- 仕事の探し方や応募方法がわからない
障害者手帳未取得の境界層(発達障害・精神疾患など)
- 「自分に合った仕事がない」と感じ、行動に移せない
- コミュニケーションや職場適応に課題
50代以上の求職者
- 「年齢が高い」という理由で採用されにくい
- 若い頃の職歴が評価されず、再就職が困難
このような人々が、どのように社会復帰を果たしたのか、具体的な事例を見ていきましょう。
支援事例①|10年以上引きこもりだった34歳男性の社会復帰
Aさんの背景
- 高校卒業後、10年以上引きこもり
- 発達障害の傾向があるが、診断歴なし
- 社会との接点がほとんどなく、働くイメージを持てない
就労支援の具他的なプロセス
🔹 第一歩:「決まった時間に通う」練習
まずは週3回、短時間の実習を通じて生活リズムを整えることからスタート。
🔹 第二歩:介護施設での実習(週3回・3時間)
清掃や食事準備など、簡単な業務を担当。実習を通じて、徐々に働くことへの抵抗をなくしていく。
🔹 第三歩:勤務時間の延長(週5回・6時間)
実習期間を経て、より長時間働くことに挑戦。コミュニケーション能力の向上にもつながった。
就労支援を行った結果
✅ 実習先で評価され、そのまま採用!
✅ 社会人経験ゼロから、介護職としてのキャリアをスタート
支援事例②|40年間引きこもりだった57歳男性の挑戦
Bさんの背景
- 10代から57歳まで一度も働いたことがない
- 両親が亡くなり、経済的に困窮
- 「外出すること」さえも不安を感じる状態
支援の具体的なプロセス
🔹 第一歩:「週1回、1時間の面談」からスタート
いきなり就職を目指すのではなく、まずは外出する練習。
🔹 第二歩:支援員とカフェで会話の訓練
社会との接点を増やし、人とのやり取りに慣れることを目標に。
🔹 第三歩:軽作業(週3日・4時間)を実習
実習を通じて、仕事への抵抗を減らし、働くリズムをつかむ。
支援を行った結果
✅ 実習先での適応が進み、現在も安定就労中!
✅ 初めは単純作業だったが、徐々に責任のある仕事を任されるように
ユニバーサル就労支援のポイント
- 小さな成功体験を積み重ねる
- 企業との連携で受け入れ体制を整える
- 社会とのつながりが意識できる
- 病気やブランクがあっても、働くチャンスはある!
「フルタイム勤務は無理…」という人でも、短時間の実習からスタートすれば、徐々に働くことに慣れていけます。また、企業側が適切なサポートを提供できる環境を作ることで、職場定着率の向上が見込めます。
そして、仕事を得ることだけでなく、社会との接点を持ち続けることが重要です。「働きたいけど、自信がない」「仕事を探しても、見つからない」と感じている方に伝えたいことは、ユニバーサル就労支援の事例からもわかるように、少しずつ社会復帰のステップを踏めば、働くことは決して不可能ではありません。
「どこから始めればいいかわからない」と思っている方は、まずは就労支援の専門機関に相談するのがおすすめです。