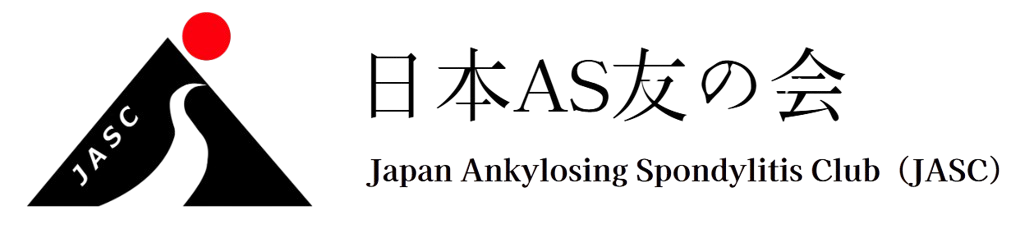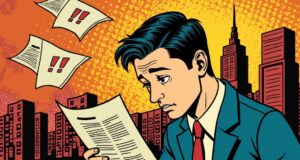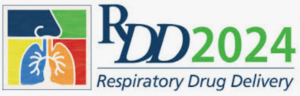日本には数百万人の難病患者がいると言われています。しかし、彼らの就労環境は決して恵まれたものではありません。
情報不足や支援制度の複雑さ、社会の認識不足が、難病患者の就職を大きく妨げています。そこで、RDD(Rare Disease Day)適職2021で取り上げられた「就労支援ネットワークONE」の取り組みをもとに、難病患者の就労課題や解決策について詳しく解説します。
難病患者の就職における課題
情報不足と制度の複雑さ
多くの難病患者は、どこに相談すればよいのか分からないという悩みを抱えています。行政や医療機関はさまざまな支援制度を提供していますが、それらが患者に十分に届いていないのが現状です。
例えば、Aさん(30代・女性)は、指定難病を抱えながらも働きたいと考えていました。しかし、就職活動を始めた際に、「どの制度を利用できるのか分からない」「支援窓口がどこにあるのか知らない」といった壁にぶつかりました。結局、自ら調べ、さまざまな機関を訪ね歩いた末にようやく支援制度を活用できることを知ったのです。
こうした情報不足を解消するためには、行政や支援団体が積極的に情報発信を行うことが不可欠です。また、患者自身も情報をキャッチしやすいように、分かりやすい形で整理される必要があります。
難病と障害者支援制度の関係
難病患者は、必ずしも障害者として認定されるわけではありません。日本では、指定難病の患者でも障害者手帳を取得できるとは限らず、障害者総合支援法の枠外となることもあります。
例えば、Bさん(40代・男性)は、難病を発症したものの、障害者手帳を取得できませんでした。そのため、障害者雇用枠を利用することができず、一般枠での就職活動を余儀なくされました。しかし、体調の変化により長時間労働が難しく、なかなか仕事が見つからないという問題に直面しました。
このように、制度の狭間にいる難病患者に対して、柔軟な支援を提供することが求められています。
難病患者の就職支援の現状
難病患者の中には、一般企業で働いている人もいます。しかし、適切なサポートを受けられる窓口が限られているため、職場環境の調整が難しいという声もあります。
例えば、Cさん(20代・女性)は、大手企業で一般職として働いていましたが、病状の悪化により通勤が困難になりました。会社に相談したところ、在宅勤務の選択肢がないため、退職を余儀なくされました。合理的配慮の不足が、このようなケースを生み出しているのです。
メディアと社会の認識の問題
重症患者に偏るメディア報道
メディアでは、難病患者といえば重症患者が取り上げられがちです。しかし、実際には軽症ながらも就職に苦労している人が大勢います。
例えば、Dさん(30代・男性)は、薬の進歩により症状が比較的軽く抑えられていますが、それでも定期的な通院が必要です。会社にその事情を説明すると、「健康に問題があるなら採用は難しい」と断られてしまいました。これは、難病=働けないという偏ったイメージが影響していると言えます。
難病患者の社会認知度と情報格差
難病患者の支援制度は、自治体や企業ごとに大きく異なります。そのため、住んでいる地域や職場環境によって、受けられる支援が異なるのが実情です。
例えば、Eさん(50代・女性)は、都内の大手企業に勤めていましたが、地方に転居した途端に支援が受けにくくなり、仕事を続けることが難しくなりました。このような情報格差をなくすためには、全国共通の支援体制の整備が求められます。
法制度と合理的配慮の重要性
障害者雇用促進法と合理的配慮
2016年に施行された障害者雇用促進法では、企業に対して「合理的配慮」を提供することが義務付けられました。これは、難病患者が働きやすい環境を作るための大きな一歩です。
例えば、Fさん(40代・男性)は、通勤が難しくなった際に、企業と話し合い、時短勤務やリモートワークの導入を実現しました。こうした合理的配慮の事例を増やし、広めることが重要です。
企業の対応と課題
企業の中には、まだ合理的配慮を十分に理解していないところもあります。そのため、難病患者の働きやすい環境を整えるためには、企業向けの研修や啓発活動が必要です。
例えば、Gさん(30代・女性)は、勤務先に配慮を求めたものの、「特別扱いはできない」と断られました。こうした認識の改善が求められています。
難病患者の就労支援の今後
RDD(Rare Disease Day)は、難病患者の就労課題を広める重要な活動です。これをきっかけに、社会全体で「難病患者も働ける」という認識を深め、支援体制を充実させることが必要です。
例えば、Hさん(20代・男性)は、RDDのイベントを通じて支援団体とつながり、適職に就くことができました。このように、情報を得る機会が増えることで、多くの難病患者が就労の可能性を広げることができます。
まとめ
難病患者の就労には、情報不足、支援制度の壁、社会の認識不足など、多くの課題があります。しかし、合理的配慮の普及や支援窓口の充実により、解決の道は開かれています。
読者の皆さんも、難病患者の就労支援について知り、情報をシェアすることで、より良い社会の実現に貢献できるかもしれません。